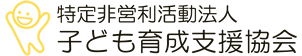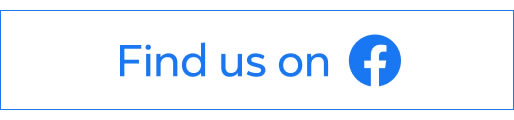《速報!今話題の玉カップがここから見れます!》
|
子育会にようこそ!
特定非営利活動法人 子ども育成支援協会(略称:子育会)では、東京都豊島区を統括本部として、埼玉県支部(日高市・秩父市・比企郡川島町)や各拠点(山形県・岐阜県・熊本県・愛媛県・青森県)をネットワークして、遊具点検の指導・研修や遊具の正しい遊び方の指導、インクルーシブ対応型遊具の開発や遊具点検業務(自治体依頼のみ)などの活動をしています。私たちは、これまでの豊富な経験や専門的な知識、そして確かなスキルと柔軟な対応力を活かして、子どもたちの笑顔のためにできることを追求いたします。活動の詳細やご相談は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
お問い合わせcontact
特定非営利活動法人
子ども育成支援協会
総括本部(代表拠点)
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-3-13-907